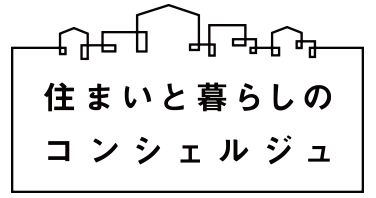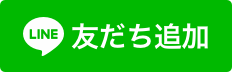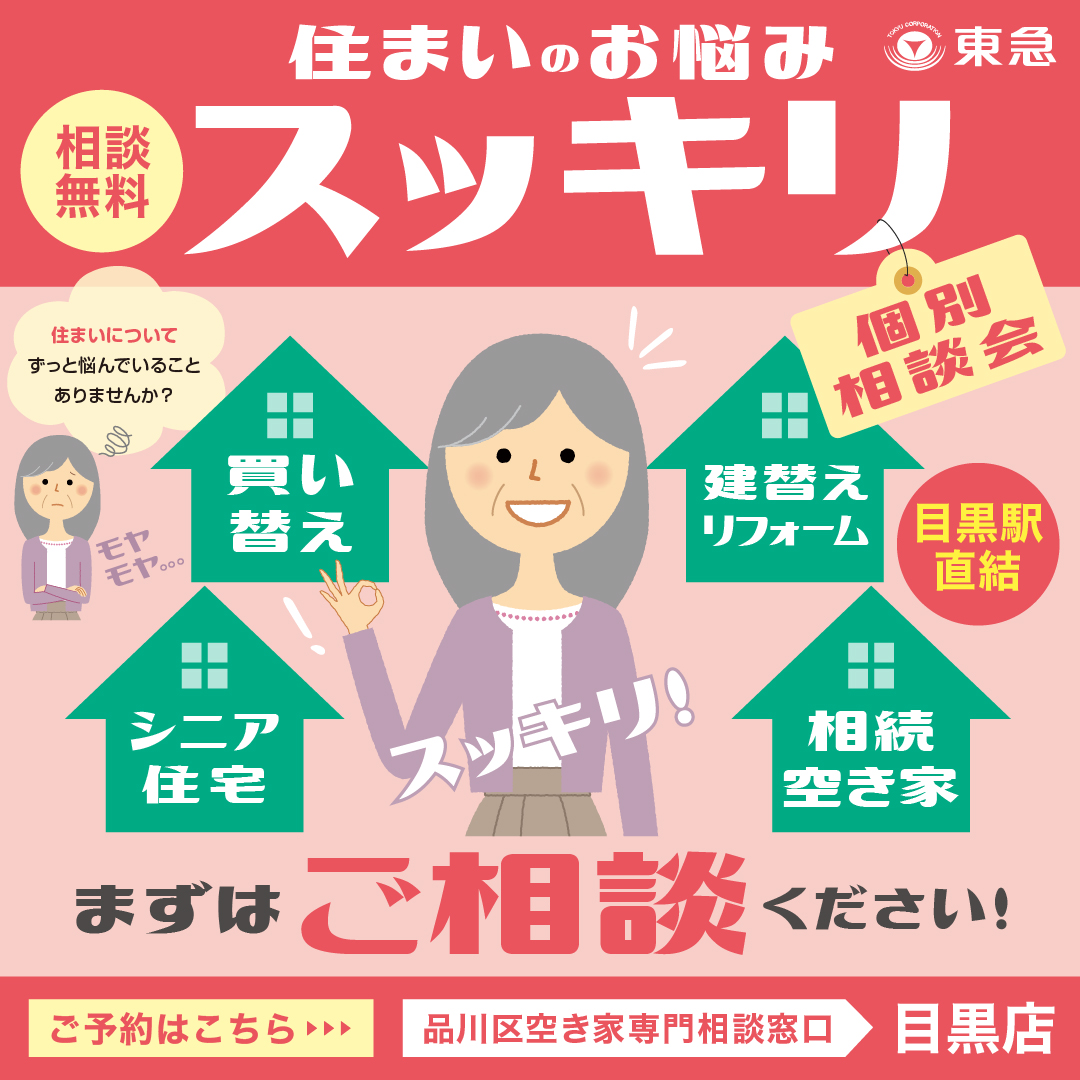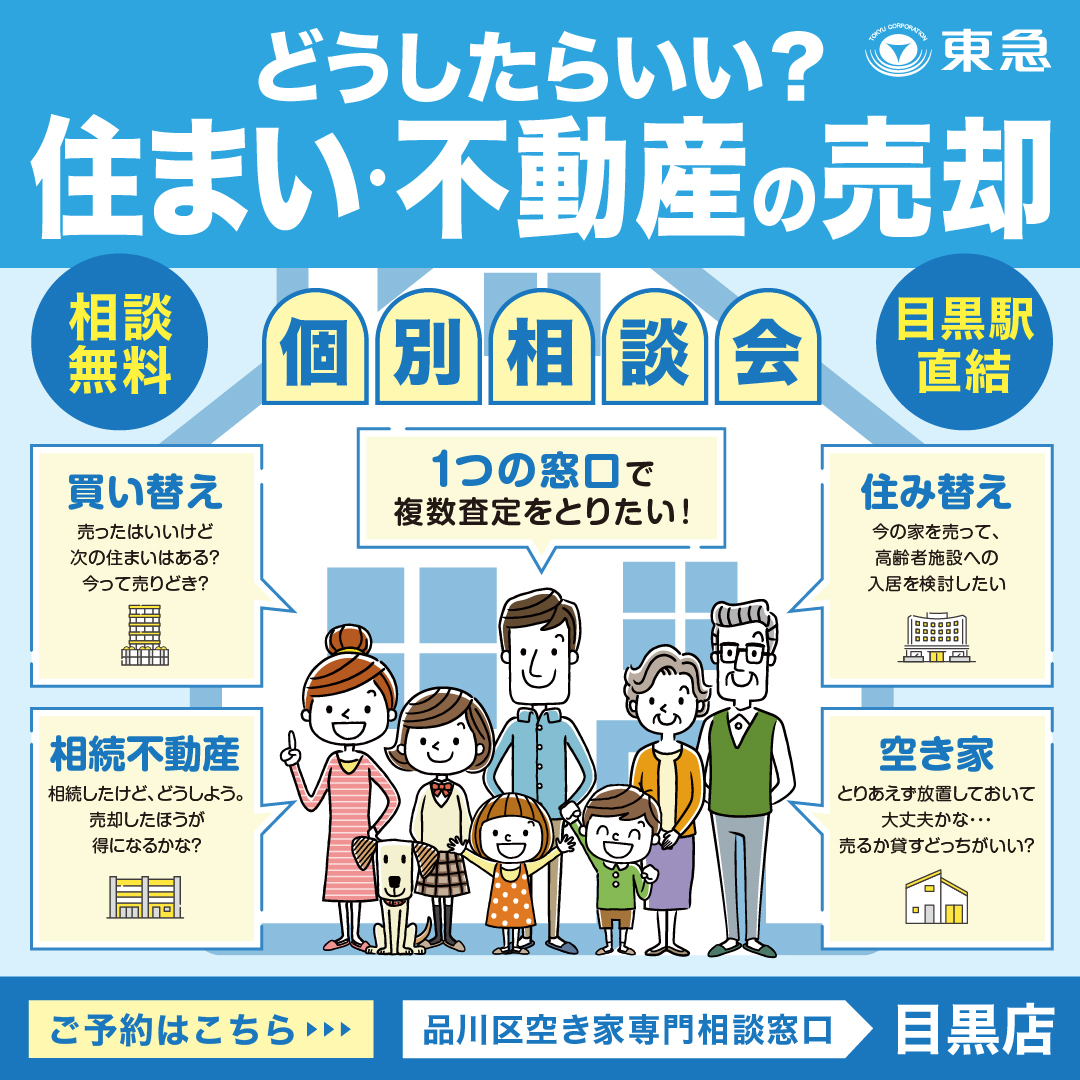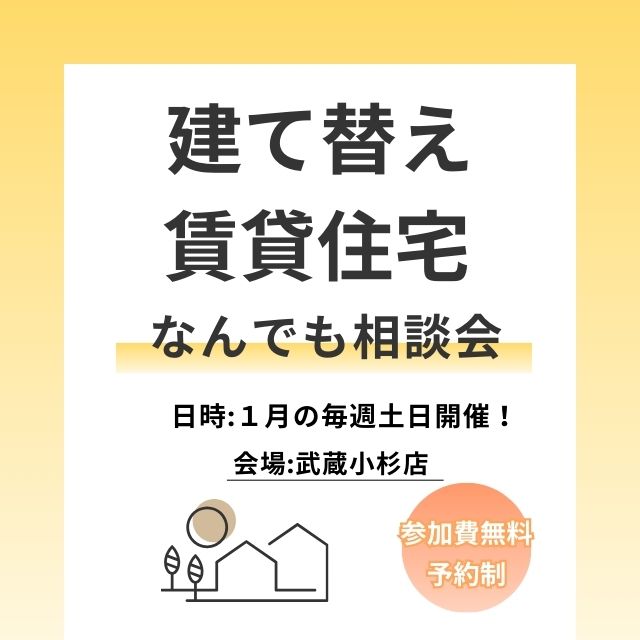| 本稿の概要 |
|---|
| ・不動産の生前贈与は相続税対策として必ずしも有効とは限らないため、個々の状況に合わせてシミュレーションすることが大切 ・不動産の生前贈与は、収益物件や将来値上がりしそうな土地の相続税対策、あるいは継承者を決めておきたい場合に向いている ・生前贈与をおこなうと受贈者に贈与税がかかり、贈与税は相続税より高負担になりやすい設計になっているため注意が必要 |
「家を相続する予定だけど、相続税が心配……」「生前贈与を考えているけど、贈与税って高いのかな?」⸺ そんな不安をお持ちではありませんか?
相続税対策の基本は、相続財産を減らすこと。ですから、相続税対策として生前贈与を検討される方が多数いらっしゃいます。しかし、贈与税の負担を考えると必ずしも得策とは限りません。
本稿では、不動産の生前贈与が相続税対策として有効かどうかを詳しく解説します。不動産の最適な引き継ぎ方法について、一緒に考えていきましょう。
不動産は相続と生前贈与のどちらが節税対策として有効か

親から子へ不動産を引き継ぐ方法には、主に《贈与》と《相続》があります。
不動産の最適な承継方法は、家族構成や財産状況、将来の計画によって異なります。また、贈与税と相続税の違いを比較し、慎重に検討することが大切です。
ここでは一般論として、生前贈与がむいている人の特徴と、相続がむいている人の特徴をご紹介します。
生前贈与がむいている人
相続よりも生前贈与がむいている人の特徴は、以下のとおりです。
- 将来、所有する不動産が値上がりしそうな人
- 特定の相手に確実に財産を承継させたい人
- 相続人が複数いて、相続紛争を回避したい人
- 早めに財産を渡したいという希望がある人
- 認知症や判断力低下の対策をしたい人
- 賃貸アパートなどの収益不動産を贈与したい人
上述の状況の人が生前贈与にむいている理由は、後述の「不動産を生前贈与するメリット」で解説します。
なお、これらのパターンに当てはまる場合でも注意が必要です。自宅は相続時に適用できる税優遇が多いため、節税面では生前贈与より相続が有利になるケースが少なくありません。
最終的にどちらの方法が有利になるかは、個々の状況によって大きく異なります。詳細なシミュレーションを実施したうえで判断することが重要です。
相続がむいている人
一方、生前贈与よりも相続がむいている人の特徴は以下のとおりです。
- 贈与税が相続税よりも高くなる人
- 相続に特有の税制上の優遇措置を活用できる人
- 相続財産の総額が基礎控除額以下の人
- 老後の資金不足が懸念される人
こちらも、理由は後述の「不動産を生前贈与するデメリットと注意点」で解説します。
相続には、生前贈与にはない税制上の優遇措置が存在します。それぞれ要件はあるものの、これらの制度を有効に活用できる場合には相続のほうが有利になる可能性が高いでしょう。
不動産を生前贈与するメリット

つづいて、不動産を生前贈与する主なメリットをご紹介します。
- 財産承継を自分の意思で計画できる
- 相続トラブルの予防になる
- 受贈者が早く有効活用できる
ここからは、上述のメリットについて詳しく解説します。内容に魅力を感じる方は、生前贈与をご検討ください。
財産承継を自分の意思で計画できる
相続は、被相続人が亡くなった際に強制的に発生します。一方、生前贈与なら「いつ・誰に・どの財産を渡すか」を贈与者の意思で自由に決められます。
たとえば「長男に自宅、長女に現金○○万円」といった割り振りを親自身の判断で決められます。そのため、遺言を書くまでもなく生前に資産配分を実現できます。
▼贈与する相手を自由に決められる
相続の場合、遺言書がないと相続人同士で遺産分割協議をおこなうことになります。その際、不動産は分割が難しく、希望する相手に確実に引き継げるとは限りません。
また、相続人以外の人に資産を相続させるのも困難です。しかし生前贈与であれば、ご自身の希望する特定の子供や孫、あるいは相続人以外の人へ不動産を譲り渡せます。
▼贈与のタイミングを自由に決められる
相続は被相続人の死亡によって発生するため、財産が承継されるタイミングを被相続人がコントロールできません。
一方、生前贈与では、贈与者が希望するタイミングで不動産を譲れます。たとえば子供の住宅取得や自身の老後の生活設計などを考慮して、最適な時期に贈与を実行できます。
他にも、以下を考慮して早めに不動産を贈与するケースがあります。
- 将来、所有する不動産が値上がりしそうな場合
- 認知症や判断力低下の対策をしたい場合
不動産の価値が今後上がりそうな場合は、早めに子に贈与しておくことで、低い評価額のうちに課税関係を済ませられます。そのため、最終的な税負担を軽減できる可能性があります。
親が高齢の場合は、近い将来、不動産活用の判断が困難になる場合があります。早めに子に名義を移しておけば、子が不動産の管理や処分をスムーズにおこなえるでしょう。
万が一、親が認知症になった場合でも、既に子のものになっていれば後見人手続きなどを経ずに活用できます。親の施設入居資金捻出のために子が売却処分する、といった柔軟な対応も可能です。
相続トラブルの予防になる
不動産は分割が難しいため、誰が相続するかでもめるケースが少なくありません。生前贈与によって事前に継承者を決めておくことで、このようなリスクを減らせます。
もっとも、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。遺留分とは、一定の相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)に対して最低限保証される遺産の取得割合を指します。
生前贈与によって特定の相続人の相続分が減少し、遺留分を侵害する可能性がある場合は、その相続人から《遺留分侵害額》を請求される可能性があります。
また、生前贈与された不動産は、相続において《特別受益》と見なされることがある点も配慮が必要です。
つまり、特別受益を受けた相続人は、他の相続人との公平を保つために、その贈与額を相続財産に加算して相続分を算定されることになります。
このような特別受益は、被相続人が「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をおこなうことで、相続分の計算に含めないようにすることも可能です。
受贈者(贈与を受ける人)が早く有効活用できる
相続の場合、被相続人の死亡後に遺産分割協議などの手続きを経て、ようやく相続人が不動産を取得し活用できるようになります。
一方、生前贈与であれば、贈与者と受贈者の合意を経て名義変更手続きが完了すれば、受贈者はすぐにその不動産を自分の判断で利用できます。
たとえば、以下のケースでは生前贈与が有効な手段になり得ます。
- 子供が住宅を必要としている場合
- 子供が事業のために不動産を活用したいと考えている場合
不動産が収益物件(賃貸アパートや賃貸マンションなど)の場合は、生前贈与を実行すると、受贈者が贈与後すぐに家賃収入を得られます。
家賃収入という将来の利益ごと不動産を引き継げる点は、生前贈与ならではの節税メリットと言えるでしょう。
不動産を生前贈与する際のデメリットと注意点

つづいて、不動産を生前贈与する際のデメリットと注意点をご紹介します。
- 相続税率よりも贈与税率のほうが高い傾向にある
- 相続時に利用できる税制優遇措置を利用できなくなる
- 相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の課税対象になる
上述のデメリットに負担を感じる方は、生前贈与より相続を優先する方がいいかもしれません。
それぞれ詳しく解説しますので、よく検討してみてください。
相続税率よりも贈与税率のほうが高い傾向にある
生前贈与の最大のデメリットは《贈与税》の税率でしょう。贈与税の税率構造は、相続税より高負担になりやすい設計になっています。
高額な不動産の贈与は税率が高くなりがちで、一度に贈与すると多額の税金を納めることになりかねません。
▼贈与税の税率
贈与税は、1年間に贈与された財産の価額に応じて累進課税が適用されます。ただし、基礎控除として「年間110万円」までの贈与は非課税になります。
親から成人している子へ贈与する場合、贈与税の税率(特例税率)は以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
たとえば、評価額が5,000万円の不動産を贈与する場合、基礎控除後の贈与税額を計算すると2,000万円を超える金額になります。ですから、高額不動産の生前贈与はあまり現実的ではありません。
なお、基礎控除分にあたる「年間110万円」以下の贈与ならば非課税となります。この制度は《暦年課税》と呼ばれ、相続税対策の王道として広く利用されています。
▼相続税の税率
相続税も累進課税が適用され、法定相続分に応じた取得金額によって税率が決まります。税率は、以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
親から兄弟のいない子へ評価額5000万円の不動産が相続された場合、基礎控除後の相続税額を計算すると「160万円」になります。
改めて、評価額5000万円の不動産を親から1人の子へ引き継ぐ場合の「贈与税額」と「相続税額」を比較してみましょう。
- 贈与税額 ⇒ 2,110万円
- 相続税額 ⇒ 160万円
ご覧のとおり、不動産では相続よりも贈与の税負担のほうが大幅に多くなるケースが少なくありません。迷ったら、税額を比較検討することが非常に大切です。
ご自身の納税額を具体的に計算したい場合は、税理士などの専門家に相談し、シミュレーションをおこなうことをおすすめします。
相続時に利用できる税制優遇措置を利用できなくなる
不動産を生前に贈与すると、相続なら利用できるはずだった税制優遇措置を利用できなくなります。とくに重要なのは《小規模宅地等の特例》です。
被相続人が居住用や事業用、貸付用として所有していた一定面積以下の土地を相続した場合、その土地の評価額を最大で80%引き下げることができます。
たとえば、自宅用の土地の評価額が5,000万円だった場合、1,000万円まで圧縮されるイメージです。小規模宅地等の特例の節税効果は、極めて大きいと言えるでしょう。
生前に贈与した土地については、原則としてこの特例を使えません。これは、生前贈与の大きなデメリットと言えるでしょう。
この他にも、相続税には特定の条件を満たす場合に利用できる税制上の優遇措置があります。
たとえば、配偶者が相続で取得した財産については「1億6,000万円」まで、または「法定相続分相当額」までは相続税が課されません。
また、不動産の所有権を子に移転する際の登録免許税や不動産取得税にも違いがあります。生前贈与で移転すると大幅に高くなります。
| 名称 | 贈与するときの税率 | 相続するときの税率 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 2% | 0.4% |
| 不動産取得税 | 本則4% | 非課税 |
以上のように、自宅不動産は相続時に大きな減税措置が設けられています。生前贈与を検討する際には、そのような側面も考慮に入れる必要があるでしょう。
相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の課税対象になる
贈与者が亡くなる前「3年以内」におこなった生前贈与は、相続税の計算上なかったものと見なされ、相続財産に持ち戻し加算されます。
この規定により、生前贈与による相続税の節税効果が一部制限されます。
また、令和6年1月1日以後の贈与については、相続開始前「7年以内」の贈与が相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
たとえば「暦年課税 (年間110万円以下の贈与は非課税)」を利用した節税スキームで自宅を贈与しても、その後7年以内に親が亡くなれば、結局その自宅分の評価額が相続税に算入されてしまいます。
高齢で健康不安がある中での駆け込み贈与は節税にならない可能性が高く、タイミングには注意が必要です。
相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、一定の条件を満たした親や祖父母(贈与者)が子や孫(受贈者)に対して財産を贈与する際に選択できる税制のひとつです。
この制度を利用することで、生前に財産を贈与する際、一定額まで贈与税が非課税になります。一方、実際に相続が発生した際は、贈与を受けた財産と相続財産を合算して相続税を計算します。
つまり、簡単に言うと「贈与税の納付を相続発生時まで延期できる仕組み」です。概要を簡単にまとめておきます。
- 課税価格:年間の贈与合計額
- 基礎控除:年間110万円
- 非課税枠:受贈者1人あたり、累計で2,500万円まで
- 贈与者:原則60歳以上の親や祖父母
- 受贈者:18歳以上の子や孫などの直系卑属
- 税率:非課税枠を超えた部分は一律20%
つづいて、相続時精算課税制度の特徴をメリットとデメリットの観点からご紹介します。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度の主なメリットは、以下のとおりです。
- 贈与時点での課税がなく、贈与税を非課税にできる
- 贈与時の税率は一定で分かりやすい
- 早期に財産を有効活用できる
相続時精算課税制度を利用すると、受贈者(贈与を受ける人)1人あたり累計2,500万円までは贈与税が非課税になります。教育費用や住宅購入資金など、大きな資金が必要なときに役立ちます。
また、非課税枠の2,500万円を超えた場合でも、税率は一律20%と本則の贈与税率より低めで、累進課税もないため計算がシンプルです。
受贈者は、早く受け取った財産を有効活用できるため、経済的に安定しやすくなります。贈与者にとっても計画的な財産承継が可能で、相続トラブルの予防につながります。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度の主なデメリットは、以下のとおりです。
- 節税効果が限定的
- 一度選択すると暦年課税が使えなくなる
- 取り消しができない
- 相続税の特例で適用外となるものがある
相続時精算課税制度を利用した場合、相続発生時に贈与した財産を相続財産に合算し、相続税として精算されます。あくまでも「納税を先送りしているだけ」で、本質的な節税効果は限定的です。
また、本制度を一度利用すると、同じ贈与者・受贈者間では「暦年課税」が使えなくなります。毎年少額ずつ相続財産を減らすという節税スキームを利用できなくなるため、注意が必要です。
さらに、本制度を一度選択すると撤回・変更ができません。長期的な税務計画が固定されてしまうため、慎重な判断が求められます。
相続税の特例(小規模宅地の特例など)で使えなくなるものがある点も、留意が必要です。
相続時精算課税制度に向いている人
生前贈与や相続に比べて相続時精算課税制度が向いているケースを整理すると、次のようなパターンがあげられます。
- まとまった資金を早期に贈与したい場合
- 贈与財産を受贈者が早く活用したほうが経済効果が高い場合
子や孫の住宅購入や教育資金など、短期間でまとまった金額を支援したいときは「相続時精算課税制度」が役立ちます。
子や孫が若いうちに資金を得て事業を展開したり資産を運用したりすることで、長期的に大きな経済的メリットが見込める場合も本制度が有用でしょう。
その他、一般的な贈与と同じく「将来的に値上がりが見込まれる財産の贈与」や「相続トラブルを未然に防ぎたい場合」にも有効な選択肢になります。
不動産の生前贈与でお悩みの方は住まいと暮らしのコンシェルジュへ
将来の価値が確実に上がる土地や賃貸アパートなどの収益物件の相続税対策、あるいは不動産を引き継ぐ人を決めておきたい場合は、生前贈与が有効な手段となる場合があります。
一方、生前贈与をおこなうと贈与された側に「贈与税」がかかります。贈与税は課税最低額が低く、累進課税率が急勾配で上昇するため、税率だけで考えると相続のほうが有利です。
また、不動産の生前贈与にはさまざまな要素が関わってきます。生前贈与をご検討で何か懸念があるようでしたら、迷わず税や法律の専門家にご相談ください。

東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」では、贈与や相続に詳しい税理士や司法書士と連携して、お客さまサポートをご提供しております。
税務や法律面のご相談も可能で、面倒な手続きもワンストップで解決していただけます。不動産の承継でお悩みの方は、ぜひ私たちコンシェルジュにご相談ください。